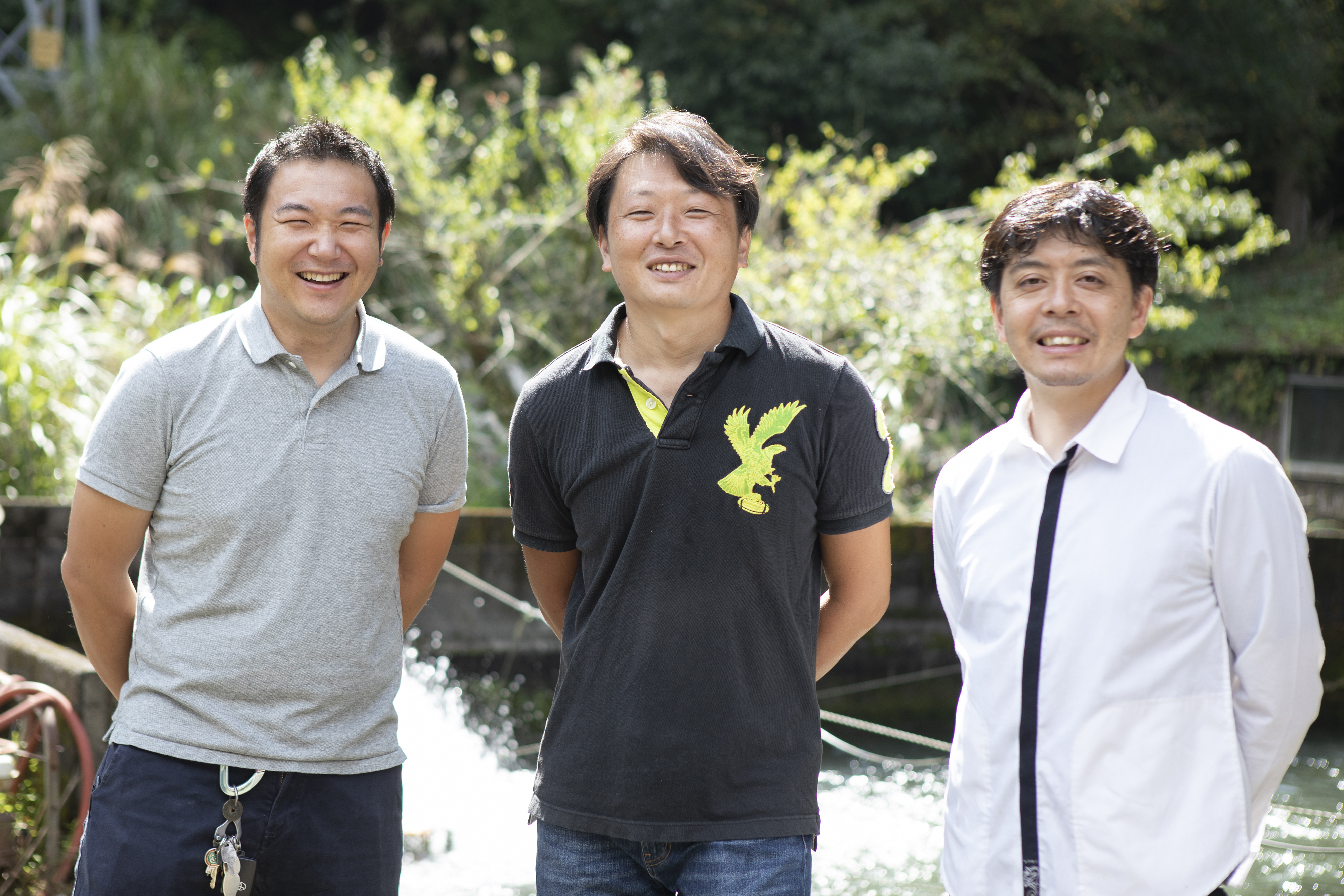山江村
山の力を、信じきるということ。
熊本県山江村と聞いて、真っ先に思い浮かぶのは「やまえ栗」だろう。山に囲まれ、水にも恵まれた自然豊かな村で、たっぷりの日光と朝霧、昼夜の寒暖差にさらされる栗は、毎年こぼれんばかりの大きな実をつける。このとびきりおいしい栗を求めて、全国の有名パティシエや料理人からのオファーは絶えず、最近では、海外からも熱いラブコールが寄せ
られるという。今回の皿の上の九州の主役は、この栗ではない。
では、なんだ?
総面積121 ㎢の約9割を森林が占め、清流・球磨川の支流である「山田川」が東部に、「万江川(まえがわ)」が西部に流れている。山江村は林業とともに発展し、山の恵みを上手に活用しながら暮らしてきた地域。すでに栗の産地としてブランドを確立した村が、2018 年度から取り組みはじめたのが、「山の恵みで豊かになる」をスローガンに掲げた「やまへ、やまえ」プロジェクトだ。
山江村特用林産物振興協議会が中心となって推進するこの事業は、「特用林産物」といわれる“山の恵み”を価値化し、林業の活性化、林家の所得向上を目指すことを目的としている。ちなみに「特用林産物」とは、ぜんまい、わらび、たけのこといった山菜やきのこ類など、森林からつくられる「木材以外」の“山の恵み”を指す。協議会は村長の内山慶治さん自らが会長を務めているとあって、思い入れもひとしお。その根底にあるのは、村人の高齢化がすすみ、後継者が減っている現状を打開し、「山江村だから生まれるもの」に光を当てたいという思いだ。

熊本県南部に位置する山江村。人口3,500 人ほどの小さな村で、8割近い農家が栗を栽培している「栗の名産地」として知られる。

日本三急流のひとつ、球磨川の支流である清流「万江川(まえがわ)」。川底が見えるほど透き通っている美しい川には、渓流の女王・ヤマメが生息している。
村ならではの山の恵みに、新たな光をあてたい。
「特用林産物を利用した商品の開発をとおして、生産者の方がつくった特産品を直接消費者に届ける仕組みづくりをすすめたい」と話すのは、山江村役場の白川満さんだ。「このネットワークを確立すれば、これまで村になじみのなかった都市圏の消費者とつながることもできます。たとえば山菜の定期便を活用したり、村に招待して農泊していただいたり、新たな交流の場を生んでいきたい」と期待を寄せる。
白川さんもこの村で生まれ、この村で育った一人。山江村の山菜の魅力をたずねてみると、「春になると、どこの家庭でも、毎日食卓に山菜が並びます。わらびご飯、わらびの味噌汁、古参竹(こさんだけ)の煮もの…、小さい頃は山菜特有の風味が苦手でしたが、やっぱり大人になってからは、しみじみとおいしいなあと思います。家庭ごとに調理方法なども違うんです。ヨソの味はわからないですけどね」と目を細める。今回皿の上の九州で出品するのは、ニオイヒバ、干ししいたけ、干したけのこ、干しわらび、干しぜんまいの5つ。三者三様の“山の恵み”について紹介する。

生産者が直接乾燥山菜を持ち込んで販売していると聞き、日用品や雑貨などを扱う『藤 田商店』に立ち寄った。店内には、干ししいたけや干しぜんまいのほか、店で加工され る味噌漬けやらっきょうの甘酢漬けなども売られていた。


写真は、ご主人の哲朗さんとともに店を切り盛りする藤田あや子さん。今年収穫した栗 でつくったという渋皮煮(コックリとした味で絶品!)をごちそうになった。創業当時 の店は、木や木炭などを運ぶ馬車引きさんたちの食事処として使われていたそうだ。
みんなで力を合わせて、みんなで豊かになる。
ニオイヒバ。あまり聞きなれないこの植物は、常用針葉樹の1種だ。手で触れるとやや硬く、モミの木を彷彿(ほうふつ)とさせるビジュアルが特徴。葉をもむと、甘いりんごのような、レモンのような香りがふっと鼻をくすぐる。現在山江村では、山江村花木生産組合のメンバー(代表:川内一郎さん)が「クジャクヒバ」と「ニオイヒバ」の2種類を育てている。
今回は、その生産組合で管理されている畑で話を伺った。日差しは容赦なく降り注ぐが、山から吹き下りる風はひんやりと気持ちよかった。その穏やかな里山の風景に見とれていると、一郎さんがバチン、とヒバを切って手にのせてくれた。8,000㎡の畑で12 年かけて育ったというヒバの幹は、思ったより太くしっかりとしている。
もともと八代市の泉町で盛んに栽培されていたニオイヒバを、山江村に持ち込んだのが川内一郎さん・美智代さん夫妻。ニオイヒバの育成は、泉町の山田さんという生産者さんから習ったものだという。「ずっと林業をメインでやっていたんだけど、年をとるとなかなか山に行けなくなるんよ。新しいことにチャレンジせんばと思ったときに出会ったのが、これだったの。栽培方法を習いにいって、メンバーに声をかけたのがはじまり。もう亡くなられてしまったんだけど、山田さんが、私たち山江村のメンバーに本当によくしてくれたとばい。もう12〜13 年前になるかな」と語ってくれたのは一郎さんだ。


長年携わってきた林業に加え、12〜13 年前からニオイヒバの生産をはじめた 川内一郎さん。70 歳を超えてなお、新たな山の恵みの可能性を信じている。
山江村のニオイヒバは、主に地元のスーパーや農協に卸され、仏花などに使われることが多い。美智代さんいわく「花にくらぶっと長くもつとよ。飾ったときに見栄えもよかしね」とのこと。生産量、売り上げともに年々増え続けており、メンバーの士気もどんどん高まっている。出荷は7月から翌年1月までと半年ほどだが、ゆくゆくは3月くらいまで出荷できる体制を整えていく考えだ。現在40 代で、いまはほかの仕事に就いている息子さんも、いずれは一郎さんを手伝いたいと話しているそう。抗菌効果やリラックス効果、消臭効果などが期待できるニオイヒバ。生産量が増えると、園芸用・観賞用はもちろん、精油やディフューザーなど、暮らしのなかで「香り」を楽しむプロダクトが生まれることも期待したい。長年自分たちの手で山を守ってきた一郎さんたちが、新たな山の恵みをとおして、こころ豊かに生きることを提案してくれる。それは少し先の話かもしれない。それでも、蒔いた種は着実に根をはり、いつか必ず、花を咲かせるだろう。

山江村花木生産組合により育てられるニオイヒバは、60cm のものと120cm の 2種類がある。生産量、売り上げともに着実に積み上がっているそうだ。

手で葉をもむとりんごのような香りがする。清涼感と存在感があるため、 部屋に置いたり、料理やお菓子の飾りつけなどにも映えそう!
山江村の空気感を丸ごと閉じ込めた原木しいたけ。
何本もの「ほだ木」が立てかけられてできるほだ場を横目に、森の空気を身体いっぱいに吸い込む。山江村の一丸(いちまる)地区で、原木栽培でしいたけを育てているのが小西候次郎さんだ。訪れたのは、しいたけの収穫にはまだ早い9月の半ば。程よい木漏れ日がさし込む、しっとりとした雑木林を歩きながら、色々な話を伺った。「ほだ木」とは、しいたけを栽培するために菌をつける原木のこと。切り出した木に穴を空け、「種駒」と呼ばれる種菌の駒を打ち付けて育成するのが原木栽培。通常サイズであれば、2夏経過の秋(種駒を打って1年半後)にぽつぽつと顔を出し始める。
お父さんの代からしいたけの育成をはじめて30 年。風味豊かで肉厚なしいたけをつくるために、一貫して原木栽培を続けてきた。扱う品種は森290 号、通称「にく丸」のみ。「50年〜60 年前までは原木を斧で刻み、自然界に浮遊するしいたけの胞子が原木に付着するのを待って育てていましたが、いまは種駒を打ち付けて、山中でじっくり育てるのが主流です」。味よし、風味よし、大きさよし。山江村特有の朝霧と寒暖差が、ぷりぷりとした食感と、うま味たっぷりのしいたけを育む。特にこの林は、直射日光があたらず、雨が適度にあたり、風通しがよく、しいたけがのびのび育つ好条件をそろえているという。
山江村では古くから、保存食のひとつとして乾燥山菜が重宝されてきた。皿の上の九州へ出品するのも干ししいたけだ。乾燥山菜は「なんとなく調理が難しそう」「戻すのが面倒くさい」というイメージをもつ方も多いかもしれないが、しいたけに関していうと、戻し方は決して難しくない。たとえば夕食の準備の際、さっと洗って水にいれて冷蔵庫に置いておくだけで、翌日の朝には戻された状態になる。味噌汁に入れたり、他の山菜と一緒に炊き込みご飯にしたり、お煮しめにしたり。炊くときに、その「戻し汁」を使うのがポイントだと美智代さんが教えてくれた。
小西さんに「山江村の魅力は?」と尋ねてみた。少しの沈黙のあと、「むつかしい質問だなあ…。うん、でも、住めば都ということでしょう」。はにかんだ笑顔を見せてくれたのが印象的だった。


風味豊かで肉厚なしいたけをつくるため、原木栽培にこだわる小西候次郎さん。山江村特有の朝霧と寒暖差が、うま味たっぷりのしいたけを育む。

丁寧に育てられたしいたけは、収穫後、まずは天日干しに。その後専用の機械で約30時間乾燥させることで乾燥しいたけになる。ちなみに小西さんのしいたけはとても肉厚のため、乾燥にたっぷり時間を要する(通常は24 時間くらい)。

山江村役場の白川満さんと吉田三奈さん。ともに山江村生まれ、山江村育ち。今後は特用林産物を活かした新たな商品開発や、県外へのPR 活動にも力を入れていく予定だ。