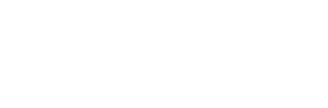2024年、JリーグYBCルヴァンカップで優勝し、初のタイトルを獲得したアビスパ福岡。2025年シーズンの活躍も期待されていますが、実は地域社会への貢献活動にも力を入れていることをご存知でしょうか。Jリーグが推進する社会連携活動「シャレン!」を活用したプロジェクト「FUKUOKA TAKE ACTION!」の取り組みでは、地元企業と連携して活動し、地域住民との交流機会を増やしています。32回目の「博多まちづくりミートアップ」では、プロジェクトの中心で邁進するアビスパ福岡株式会社マーケット開発部の佐川諒さんに、プロスポーツチームと取り組むまちづくりについて伺いました。
一般企業で営業力を磨き、憧れのスポーツビジネスの世界へ
岸本:
今回は「地域愛が原動力 アビスパが地元企業と作る福岡の未来」がテーマです。福岡には多くのスポーツチームがありますが、直接関わる機会は意外と少ないですよね。そんな中、アビスパ福岡(以下、アビスパ)は「もっと地域と一緒に」と積極的に活動されています。地域や企業とプロスポーツがつながり、まちを盛り上げるにはどうすればいいのか。プロジェクトを推進されている佐川諒さんと一緒に考えていきたいと思います。
佐川:
Jリーグクラブ「アビスパ福岡」の佐川諒です。よろしくお願いします。
私は、アビスパのリージョナルイノベーション戦略部という部署で働いています。スポーツを活用した新規の事業を作ることをミッションに、スポーツ界でどこのチームもやったことがない新しい事業の柱を作って、持続可能なスポーツビジネスの確立に向けて動いています。
岸本:
佐川さんは神戸出身ですよね。どういった経緯でスポーツビジネスに関わるようになり、福岡へ?
佐川:
私が通っていた大学がヴィッセル神戸のスポンサーだったこともあり、ヴィッセル神戸の社員の方によるスポーツビジネスの講義があったんです。その講義を受けて「スポーツチームで働きたい」と思いました。ただ、業界に憧れて入ってもスキルがないと続かないと考え、大学卒業後はスタートアップ企業へ。でも、リーマンショックで入社75日で給与支払いができないことになり。キャリアに悩んだ経験を活かしてキャリアサポートにつながる仕事と自分の営業スタイルを構築する武器を身に付けることができればとの思いがあってリクルートに入社し、後に東京ヴェルディへ転職しました。
岸本:
東京ヴェルディではどんな仕事を担当されていたのですか。
佐川:
主にスポンサーセールスです。当時は「看板300万円でどうですか?」というカタログ営業スタイルでしたが、企業の皆さんはどれくらいの予算を使い、どんな効果や価値が出るのか、シビアに考えられています。このスタイルは長続きしないと考え、企業の課題に対し「スポーツをこう活用できますよ」とオリジナルプランでカスタマイズして提案する形に変えました。スポンサーとの関係は単なる広告ではなく、ビジネス的な価値を提供するものにしないと生き残れません。
岸本:
知名度の生かし方や露出の使い方を見直し、企業のニーズに応じた提案型の営業に転換したということですね。
愛するJリーグクラブを守り、成長させるだけの力を求めて
岸本:
では、アビスパへ移ったきっかけは何だったのでしょう。
佐川:
私が所属していた当時、ヴェルディはJ2で14年目。「クラブを復活させる」と思っていましたが、経営難や資金不足に直面し、自分にはまだ大きな経済を動かす力がないと痛感しました。営業部長の立場では本質的な変革に関われない。そんな時、「新規事業を任せる」と声をかけてくれたのがアビスパでした。社長直下の部署で、Jリーグクラブ経営に最短で関われると思ったんです。
岸本:
福岡に来てみてどうですか。
佐川:
2年半で8kg太りました(笑)。福岡は人とのつながりが強く、飲み会も多い。関西に似ていると思っていましたが、それ以上に「この人が頑張っているなら助けよう」という文化が根付いていると感じます。
20億の収益差解消に向け、企業やサポーターを巻き込む取り組みへ
岸本:
では、アビスパでの活動についてお聞きします。Jリーグクラブはどのように収益を得ているのでしょうか?
佐川:
主な収益は、①スポンサー広告収入、②入場料収入、③グッズ売上、④スクールの分配金、⑤放映権の分配金の5つです。アビスパの売上規模は31〜32億円ですが、J1の平均は50億円。平均と比べて約20億円の差があります。僕の部署の役割は、その差をどう埋めるかを考えることです。
岸本:
20億円の差は大きいですね……。
佐川:
ちなみに昨年、ルヴァンカップ決勝で戦った浦和レッズとは、80億円の差がありました。それでも勝てた。サッカーはチーム力や監督のマネジメント力で勝負できるスポーツなんです。
岸本:
お金を出せば勝てるわけじゃない。そのドラマ性こそ、地域企業がプロスポーツに関わる価値があるのですね。
では、アビスパのマーケット開発部ではどんな取り組みをされているのでしょう。
佐川:
まず「スポンサーセールス」。地元企業だけでなく、東京や海外の企業とも交渉し、大型契約を獲得する仕事です。
次に「Web3関連事業」。アビスパは日本初の「スポーツDAO(分散型自律組織)」を立ち上げました。一定数のガバナンストークン(※)を持つ人がクラブの意思決定に関われる仕組みです。例えばユニフォームのデザインを投票で決めるなど、ファンが運営に積極的に参加できる仕組みを作っています。
※ガバナンストークン:DAOの運営に関わる意思決定や報酬の分配などに使用される暗号資産。保有者はコミュニティの参加権や投票権など特定の権限を得ることができる。
岸本:
デジタル版の株主のようなイメージですね。
佐川:
そうですね。ただ投資目的ではなく、本気でクラブを応援したい人が集まっています。現在3,000〜4,000人が参加していますが、ある展示会で人手が足りない時、「手伝います」と名乗り出てくれる方もいたんです。
岸本:
従来の「お金を払ってチケットを買い、試合を観戦して帰る」という関わり方ではなく、まるでクラブの“中の人”になれるような、新しい形のコミュニティが生まれているんですね。
佐川:
そうなんです。スポーツDAOでは「福岡のまちをどう良くしていくか」という議論が進んでいます。デジタル領域とリアルな地域課題を掛け合わせて、課題解決に取り組むプロジェクトチームが立ち上がっているんです。
岸本:
オンラインコミュニティからリアルな行動につながる、今まさに新しいステージに進んでいるということですね。
ほかにはどんな取り組みがあるのですか。
佐川:
3つ目は「DXパートナー」です。アビスパ福岡では、「アビスパ・グローバル・アソシエイツ」という支援組織があり、毎月60人ほどの経営者が集まり、アビスパの経営陣と前月を振り返る情報交換会を続けています。この場を通じて、東京のIT企業と九州の企業がつながり、DX推進や新規営業の機会が多く生まれているんです。
岸本:
プロスポーツチームとしてのブランド力を、地元企業がビジネスのために活用できる。多くの企業は「プロスポーツチームは遠い存在」と感じていたと思いますが、実はその知名度をうまく使えるというのがおもしろい点ですね。
佐川:
そうです。そして4つ目の「アジア戦略」。2年前にバンコクのクラブと提携し、選手やアカデミーの交流を実施。タイの選手が加入すればインバウンドツアーの展開も可能です。Jリーグの育成メソッドを販売するクラブもあり、アビスパ独自のメソッドを確立すればアジア進出の道が開けます。サッカー教育に加え、食育や語学なども組み合わせ、企業とともに海外展開を目指しています。
岸本:
アビスパと組むことで、企業が新しい切り口で海外に進出できるんですね。