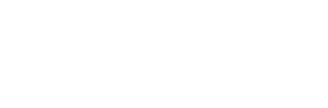佐賀の山には、自然環境で生活する知恵を伝えたり、山の恵みを使った料理店を営んだりと、さまざまな分野のプレイヤーが関わり、地域の暮らしを支えています。「YAMAOSM」は、そんな山を愛する皆さんと一緒に作られているプロジェクトです。後編では、「YAMAOSM祭」に参加した3人のプレイヤーをクローズアップします。
自然の中で生きる術を学び、山に寄り添った暮らしを
まずご紹介するのは、三瀬地区の山の中に設けたキャンプフィールドを中心に、ブッシュクラフトの普及活動などを行う「タネマフタ三瀬」です。ブッシュクラフトは、Bush(茂み)とCraft(工作、工芸)を組み合わせた造語で、「自然環境における生活の知恵」という意味をもちます。道具に頼りきるのではく、まわりにある自然の素材をうまく使う知恵が身につくため、自身の力で生きている感覚を味わうことができます。

タネマフタ三瀬の川越さん。タネマフタは、ニュージーランドにあるカウリの木の名称で、原住民マオリ族の言葉で「森の神」の意味をもちます
講座で使用するキャンプフィールドは、森林を伐採せずに、できるだけありのままの自然を残しています。一般的なキャンプ場と違って、電源設置がなければ炊事棟や販売所もありません。視界に人工物が入らない場所で、参加者は自然と真っ向から向き合います。「文明が発達するまで、人類は自然と共存してきました。焚き火を見るとほっこりした気分になるなど、自然に寄り添う感覚は現代人にも残っているはずです。その感覚を、ブッシュクラフトを通して呼び覚ましてもらえたら嬉しいです」。

不便さを自然の素材で補うブッシュクラフトは、ファミリーキャンプとはひと味違った魅力があります
ブッシュクラフトのBASIC講座は、タネマフタ三瀬のホームページから申し込むことができます。道具の少なさを自然素材で補う経験は、自然のありがたみを再確認する機会になるはずです。一人一人が自然との繋がりを深めることで、地域と山の距離感が少しずつ縮まっていくのではないでしょうか。
中山間地域の未来を見据えて、地域循環型農業を実践
続いてご紹介するのは、脊振町の山地で、日本でも希少な平飼いの鶏を育てている本間昭久さんです。ご自身が経営する本間農園でお話を伺いました。昨今、多くの中山間地域で過疎化が進み、廃業する農家や閉店する商店が増えています。このような状況のなかで、本間さんは「YAMAOSM」の活動に、「多くの方が佐賀に足を運び、自然に触れて感動する。それを見た地域の方々が地元の価値を再確認するという、相乗効果が生まれれば」と期待を込めます。「YAMAOSM祭“やまのば”」では、自家飼育の卵を使ったスイーツなどを販売。今後も、「イベントやSNSを通じて、生産者の理念など、商品の背景にあるストーリーを伝えていきたい」と話します。
農園を営む前から、農業人口の減少を見据え、地域内で農業を持続させることの重要性に着目していたという本間さん。2008年に養鶏を始めると、地域に根ざした循環農業を導入しました。その取り組みを象徴するのが、堆肥の発酵熱を利用した養鶏法です。本間さんは、「ヒヨコたちは温かい寝床でストレスなく過ごすことができます。また、常在菌に触れることで免疫力が高まり、健康な鶏へと成長します」と、そのメリットについて語ります。
しかし、寝床をつくる作業は、決して楽ではありません。新しいヒヨコを迎える度に、藁と鶏糞を踏み込み、まる一日かけて9層ほど堆積。ガスや電気と違って手間と時間を要するため、日本で取り入れている農家はごくわずかだといいます。本間さんは、「堆肥は敷き始めがもっとも温かく、生まれたてのヒヨコをしっかり温めます。その後は徐々に発酵が落ち着くため、ヒヨコの成長スピードとうまく噛み合います。準備は大変ですが、自然に温度調整されるので、ダイヤル操作の必要はありません」と笑みをこぼします。
また、飼料に含まれる米糠やおからなどには、地元産業からの副産物を使用。さらに、農場内で刈り取った草を与えるなど、できる限り地域の中で飼料を調達するよう努めています。
「観光資源が乏しくても、人を呼ぶことができる、生計を立てることができるという、地域における持続可能性を実証したい」と語る本間さんは、新たな活動にも取り組んでいます。クラウドファンディングによって実現したゲストハウスでは、日本だけでなくフランスやマレーシアなど海外の観光客もファームステイを満喫。さらに、農家レストラン(カフェ)や、あえて不便さを楽しむ宿泊施設の計画も進行中です。価格高騰やその他の情勢に左右されない、地域内における循環経済の構築を目指して、本間さんは「持続可能は目標ではなく大前提です」と気を引き締めます。
自然の恵みと、生産者たちの情熱が詰まった“小さな山”
最後に、佐賀県庁近くでおむすび店のしろいしもりを営む森卓也さんにお話を伺いました。卓也さんは、佐賀県中南部の白石町で、干拓地ならではの肥沃な土壌が広がるこの地で、弟の慎二さんと力を合わせて海苔と米の栽培を行う生産者でもあります 。
海産物や農作物を育てるうえで、山の自然は必要不可欠です。山に降った雨は、ミネラルなどの養分を吸収し、河川を経由して有明海に流れ込みます。また、ダムから引いた田んぼの水も、もとをたどると山の水です。その自然があるからこそ農漁業が成り立ち、佐賀が誇る美味しい食材が供給されるのです。
卓也さんたちが漁場としている有明海は、干満差が日本一といわれる国内有数の海苔の生産地です。卓也さんたちが育てる海苔は、佐賀県が開催する品評会で過去に「佐賀海苔有明海一番」の称号を獲得。高い品質の裏には、「海苔は手間をかけたぶんだけ美味しくなる」という深い情熱が隠されています。「干満の差に頼らずに、自分たちで海苔網を上げ下げしています。ほぼ一日がかりの作業ですが、適切に乾燥させることで、風味や香りが格段に増すんですよ」。
いっぽう米は、二毛作によって栽培。麦わらを土に返し、微生物と混ぜて有機物を分解させることで、栄養たっぷりの土壌をつくります。さらに、酵素を含んだ肥料を与えるなど、地域の先輩農家にアドバイスをもらいながら米づくりに励んでいます。
しろいしもりに並ぶおむすびには、そんな自然の恵みと、卓也さんたちの愛情がたっぷり注がれています。ふっくらとしたご飯の中には、牛肉や鯖、チーズなど、主に佐賀県内で作られた食材が入っています。実は当初、おむすびではなく、米と海苔のセットを販売する予定だったとか。しかし、地元の生産農家と接するうちに、地元の恵みを詰め込んだおむすびにする決意を固めました。
卓也さんは、「どなたも、美味しいものを食べてもらいたいと、プライドをもって作物を育てています。しかし、その魅力をアピールする場がないため、安く販売する方も少なくありません。しっかりブランディングすれば、世の中にきっと価値が伝わるはず。このおむすびがきっかけとなり、佐賀の一次産業がもっとフォーカスされるようになったら嬉しいですね」と胸を膨らませます。
山と密接に関わるプレイヤーと、少し離れた立場から関わるクリエイター。立場は異なりますが、山を大切にする気持ちは共通していました。そんな皆さんが、「YAMAOSM」で業種の垣根を超えて一つになることで、佐賀の山を思う人の輪は広がっていきます。
野菜や魚を味わうときに、プレイヤーに思いを巡らせる。少しの間だけ便利さを手放し、自然の中で過ごしてみる。日々の行動の一つ一つが、山の価値を見直す貴重なステップになります。「YAMAOSM」の活動に触れてみて、あなただけの佐賀の山の入り口を見つけてください。
YAMAOSMのウェブサイト
https://yamaosm.com/
YAMAOSMのInstagram
https://www.instagram.com/yamaosm_saga/
(取材:編集部、文:ライター/岩﨑 洋明、写真:カメラマン/勝村 祐紀)