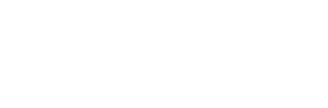プロスポーツチームとの取り組みで、社会貢献活動に価値を生み出す
岸本:
「アビスパと地域との関係性を築く」とは、具体的にどういうことですか。
佐川:
Jリーグ全体の「シャレン!(社会連携活動)」の一環として、アビスパも年間約2,100回の地域貢献活動(ホームタウン活動)を行っています。2023年からは、企業・自治体・NPOなどと連携し、社会課題の解決を目指す枠組み「シャレンパートナー」と企業の皆さんと推進するプロジェクト『FUKUOKA TAKE ACTION!』を発足。Jリーグの知名度を活かし、スポーツ以外の分野にも貢献できるようになりました。企業の社会貢献活動としての認知度が上がることで、単なるボランティア活動以上の価値を生み出しています。
岸本:
企業単独の取り組みでは伝わりにくい活動も、アビスパと組むことで明確な価値になるんですね。
佐川:
そうです。さらに、企業のサステナビリティレポートにも活用できます。今の時代、環境や社会に貢献しなければ事業価値を高めにくいですが、日本ではまだ十分に浸透していません。企業が単独で進めるよりも、サッカークラブを活用し、多くの人を巻き込んで実績を作る。これが私たちの提供できる大きな価値です。
岸本:
これまでにはどんな経緯で、どのようなプロジェクトが立ち上がってきたのですか。
佐川:
地域と関わることで、まちの課題を知る機会が増えます。その課題を企業が知り、ソーシャルビジネスに発展させることで、新たな価値が生まれます。そこで毎月15〜20社と社会課題の勉強会を開催し、その学びを活かしたプロジェクトが現在22個進行中です。
例えば、スポーツツーリズムでは、アウェイのサポーター向けに試合前後の観光情報を提供するプラットフォームを構築。博多阪急やチャリチャリなど、福岡の企業6社と連携し、地域経済への貢献を実現しています。
岸本:地域企業がサポーターを迎え入れ、経済的なメリットを得る。これはWIN-WINの関係ですね。
佐川:そうです。アビスパの社員は約30人と少なく、スポーツ業界の知見だけでは新たなビジネス創出は難しい。だからこそ、企業や自治体が当事者となり、チームを活用して社会課題を解決する。この仕組みが重要なんです。
さらに、スポーツには感動があります。試合の勝敗で涙することもある。スポーツチームと一緒に取り組むことで、社会貢献活動を”心を動かす体験”につなげることができると思うんです。例えば、以前、介護施設に訪問した際、ご年配の方に応援用のユニフォームをプレゼントしたことがありました。認知症の症状が出ていて、普段感情をほとんど表に出さない方がとても喜ばれていて、スタッフの方が驚かれたことがあって。僕もその話を聞いて、胸が熱くなったんです。
岸本:社会課題への取り組みが、表面的な活動ではなく、深い意味を持つようになっているんですね。
佐川:スポーツチームには多様なステークホルダーがいますが、好きなチームが発信することで、普段関心のない社会課題にも目を向ける人が増える。この“影響力”こそ、私たちが提供する価値です。
アビスパを軸に仲間を増やし、つながりを活かした深い取り組みへ
岸本:
企業目線でうかがいますが、アビスパにとってのメリットはあるのですか。
佐川:
率直にいうと、収益につながる点が大きいです。スポーツ団体は「ボランティアでやるべき」という考えもありますが、持続性がない。だからこそ、地域貢献を事業として成立させることが重要です。
もう一つは、「仲間が増えること」。現在48社がプロジェクトに参加し、試合結果に関係なく「アビスパとまちを良くする」ことに価値を感じています。このつながりが新たな連携や成功事例を生み、加速しているんです。
岸本:SDGsや社会貢献活動って新しい形ですね。ただ、こうした活動は多くの企業で「人事部の誰かが片手間で担当している」といったケースが多い。その中で、アビスパの取り組みは、企業の社会貢献活動に関わる部門を一段押し上げるほどの影響力を持っていると感じます。
佐川:ありがとうございます。実際に、当初は「地域貢献活動の一環」として見られがちでした。しかし、今では持続可能性を重視し、企業との横の連携を強化することで、より深い取り組みに発展しています。
岸本:これまでの2年間で手応えを感じていると思いますが、今後の展望を教えてください。
佐川:最初は社内でも猛反対されましたが、8社から始まり、2年目には48社が参加していただきました。まずは「広く浅く」を意識し、クリーン活動やブラインドサッカーなど、誰もが関われる形で進めていたんです。
3年目からは「深さを追求」するフェーズに入ります。例えば、少年院の子どもたちの社会復帰支援や、福祉事業所の方々がスタジアム運営に関わる場を作る取り組みです。さらに4月からは、学生向けのソーシャルリーダー育成や起業家育成プログラムも開始予定です。企業とともに、新たな価値を生み出していきたいですね。
岸本:それでは、ここで参加者の皆さんの質疑応答のお時間に入りたいと思います。
参加者:企業としてのメリットや成功事例、収益性より貢献を重視する企業の具体例を教えてください。
佐川:シャレン!のパートナー企業は新規事業担当者が多く、直接の利益よりも実績作りを重視する傾向があります。例えば、スポーツツーリズムのプロジェクトでは、アビスパの事例が他地域にも広がり、アプリ開発会社がプラットフォームの中心的存在になりました。
また、収益より地域貢献を優先する企業もあります。オリンピック・パラリンピックのスポンサー企業が、地域で成功事例を作り、それを全国展開するケースもありました。スポーツチームとの協業により、地域に根ざした活動を通じてブランド価値を高めています。
質問者:サッカーだからこそできること、逆に他のプロスポーツではできないことについて、どうお考えですか。
佐川: Jリーグは「100年構想」を掲げ、地域密着型のクラブ運営を行っています。そのため、クラブの地域貢献は当たり前で、ファンにも違和感がありません。これが、プロ野球やバスケとの大きな違いです。例えば、プロ野球は企業スポーツの色が強いですよね。
一方、Jリーグは地域とのつながりが前提なので、企業も参画しやすい。さらに、サッカーは世界共通のスポーツです。アジア市場を狙う企業にとって、Jリーグクラブとの協業は魅力的な選択肢になります。
質問者:
昨年初めて観戦しましたが、ファンに年配の方やファミリーが多いことに驚きました。地域に根付いている証だと感じましたが、マネタイズ抜きで「やりたい!」と思うことはありますか?
佐川:
サッカーチームの集客を短期・長期の時間軸で考えています。短期的には、日本代表ユニフォーム配布や地元アーティストとのコラボなど、エンタメ性を活かして観客を増やす。長期的には、ゴミ拾いなど地域活動を通じてサッカーに興味がない人とも接点を持ち、「アビスパは福岡のために頑張っている」と認識してもらうことで、未来の観客を育てます。そのため、地域密着の専門チーム設立を進めており、今朝も議論したばかりでワクワクしています。
福岡のまちのためになる、スポーツの価値を提供し続けたい
岸本:
本日はお時間をいただきありがとうございました。最後に、佐川さんから今シーズンの意気込みをお願いします!
佐川:
私自身、福岡に来て3年目が終わり、4年目に突入します。今年は個人としても大きな勝負の年になり、将来的にはJリーグのチェアマンになりたいという夢も持っています。そのためにも、アビスパで経営に近い立場に立ち、自分の意思決定を活かしながら、福岡のまちのためになるスポーツの価値を提供し続けたいと考えています。
今年は監督も変わり、クラブ創設30周年という記念すべき年です。過去最高の成績を目指し、選手・スタッフ一丸となって頑張りますので、ぜひスタジアムに足を運んでください!