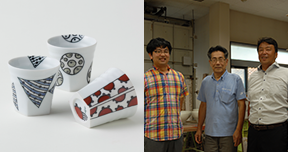一年で水やりはたった一度きり
一年で水やりはたった一度きり
予約待ち、実に4ヶ月。佐賀市で農家を営む永尾真治さん、その名も「永尾産ち」のトマトだ。育てているのは甘みが強くフルーツ感覚で食べられる一口サイズの「小鈴」、高糖度で果皮が薄い中型の「フルティカ」、一般的に市場に出回っている大玉「桃太郎」の3品種。飲食店をはじめ個人宅配や店舗での対面販売が中心だ。
栽培には化学肥料を一切使わず、農薬も必要最低限。その分土づくりにすべてを注ぐ。土に欠かせないのが、有機質肥料に土やもみ殻などを混ぜて発酵させた「ぼかし肥料」だ。永尾さん自身「企業秘密」と称するこの「ぼかし」を土と混ぜ合わせることによって、年々肥沃な土壌がつくられ「トマトの味もどんどん良くなっている」ほど。
できるかぎり農薬を使用しないため「菌は持ち込まない」のも永尾さん流。植え付け前には、畑をビニールで覆って土壌温度を上げることによる温湯消毒を実施。ハウス内には虫取りテープをいくつもぶら下げ、靴の裏に付いた菌も極力入れないように普段は取材もNGという徹底ぶりだ。
さらに驚くのは水やりの回数。一本のトマト苗が発芽して実をつけ、その役目を終えるまでおよそ10ヶ月。その間に水をあげるのは、初期に苗を定植したときの一回のみ。「水をやらずとも自分で地中深くに延びていって、結果的に根が強くなるんです」と永尾さん。苗は最長で50メートルにまで成長し、全盛期のハウス内は苗とたわわに実るトマトでいっぱいになる。
土づくりも、菌を入れないことも、水をあげないことも、何より「あとあと自分がラクだから」と永尾さん。「農業と言えば、3K=キツイ・キタナイ・カセゲナイ。そうではなくて、ラク・タノシイ・カセグにしたい」と、これから先の農業を語る。

植え付け4日目の苗。一度きりの水やりは終わり、これからは自力で根を張っていく。昼間は暑さでしんなりしても夜には元気を取り戻し、これを日々繰り返していくうちに強い苗に育つ

苗は支柱に沿うようにハウス内を張りめぐり、最長で50メートルにも達する

ハウスの周囲には防虫ネットを完備。内部に見える黄色い短冊状のものは虫取りテープ。虫や菌を取り除く工夫がいたるところにある

トマトの栽培には、この「ぼかし」が欠かせない。原料のひとつ、ホタテの貝殻を細かく粉砕した石灰は、わざわざ北海道から取り寄せる
値段は3倍。なのになぜ売れる?
代々続くトマト農家を永尾さんが引き継いだのは6年前。それまで車の整備会社で技術士として将来を嘱望されていた永尾さん自身、「農家になるとは思ってもみなかった」。
思わぬ転機となったのは、ハウスの周囲に張りめぐる熱線がショートして発火し、ハウス内のトマトが枯れてしまったこと。折しも収穫前日の出来事だった。
「落ち込む父親を見て、自分がなんとかしなければと」立ち上がった永尾さんがその時父親から教えられたのが「植物も人間と同じ」という育て方だ。「枯れた苗とトマトの実」を、「やけどを負った母親とその子ども」と見立てて、懸命に自己流の“治療”を施した末、復活するのを目の当たりにした永尾さん。「普通は枯れたら引っこ抜くでしょう。でも父はそうはしなかったんです」。この体験は、永尾さんにとって眼から鱗だった。
就農を決意した永尾さんがまず力を入れたのは、販路の拡大と対面販売。栽培方やトマトの味は親の代で確立されていたが、地元でしか販売していなかった。「自らの足を運ぶ」ことにこだわり、店の大小や場所を問わずトマトの質を認めてくれる取引先に出向き続けた結果、今や九州から関東まで飛び回るまでになった。出張先の対面販売では、多い日に2000パックのトマトを売り上げることもある。
「質を認めてくれる人に売る」ことはつまり、価格を自分で決められること。これが農協に頼らない自立した農家につながった。値段はふつうのおよそ3倍。「高くても美味しければ必ず買ってくれる人がいるんです。だからこそ美味しいトマトをつくろうと思える。自分のつくったものが人の笑顔に結びつくなんて最高じゃないですか」と、笑顔で話す。

自ら「営業が好き」というだけあって、次から次に展開される農業トークには耳を傾けずにはいられない。後ろに見えるのは、永尾さんが栽培している米とトマトのハウス

商業施設内にある地元の農産物直売所などで定期的に対面販売。「お客さんと直接向き合う」行為を大切にしている
今の世の中、一番楽しいのは農業
北は脊振山地、南は有明海に囲まれ、その温暖な気候で古くから稲作を中心に栄えてきた佐賀。永尾さんの畑は、見渡すかぎりの田畑が広がる佐賀平野の一画にある。そばにはいくつもの溜め池や用水堀があり、昔から雨だけが頼りで水が不足しがちだった佐賀平野の歴史を感じさせてくれる。
この地でトマト以外に米も栽培している永尾さん。田植え前にレンゲの種を蒔き一面に花を咲かせることで、土の栄養価が上がるうえに稲が強く育つため、化学肥料や農薬を極力減らすことができる、いわゆる「レンゲ米」だ。春になると一面ピンク色に染まるレンゲ畑を開放し、「少しでも農業の楽しさに触れて欲しい」と、子どもたちが走り回ったり野花を摘んだりできる環境を提供し、一般の人々と触れ合う機会を何よりも大切にしている。多忙の合間を縫って対面販売をこなすのも、その理由からだ。
永尾さんは現在、佐賀の若手農家3組と新しい農家の可能性を模索中。佐賀から全国へ、ゆくゆくは海外まで視野を広げながら、農業の未来図を描く。再来年には、畑の近くに直売所圏カフェをオープン予定だ。
「今までの農業をぶっ壊す覚悟でやっていかないと、日本の農業に道はない」。そう言い切きりながらも、「でも今の世の中、農業が一番楽しいですよ」と豪快に笑う永尾さん。そこから感じるのは、危機的な日本の農業に対する深刻さというよりはむしろ、農業には他にはない可能性があるという確信だ。

古くから日本一の米どころとして栄えてきた佐賀。平地のいたるところには、溜め池やクリークと呼ばれる用水堀がある